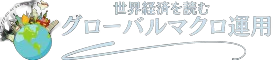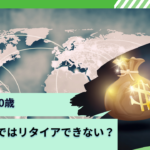日本の個人投資家の間でも、近年成長著しい南アジアの株式市場に注目が集まっています。
本記事では、南アジアに位置する インド、スリランカ、バングラデシュ それぞれの株式市場について、市場の構造や主要な株価指数、経済成長との関係性、注目される業種・企業などを踏まえ、10年以上の長期スパンでの現状と将来性を詳しく解説します。
さらに、日本人投資家がそれぞれの国に投資するための具体的な手段(現地証券口座の開設、日本国内で購入可能なETF・投資信託、ADR〔米国預託証券〕など)についてもまとめます。投資初心者の方にも分かりやすいよう、ポイントを整理しながら説明していきたいと思います。
Contents
インドの株式市場
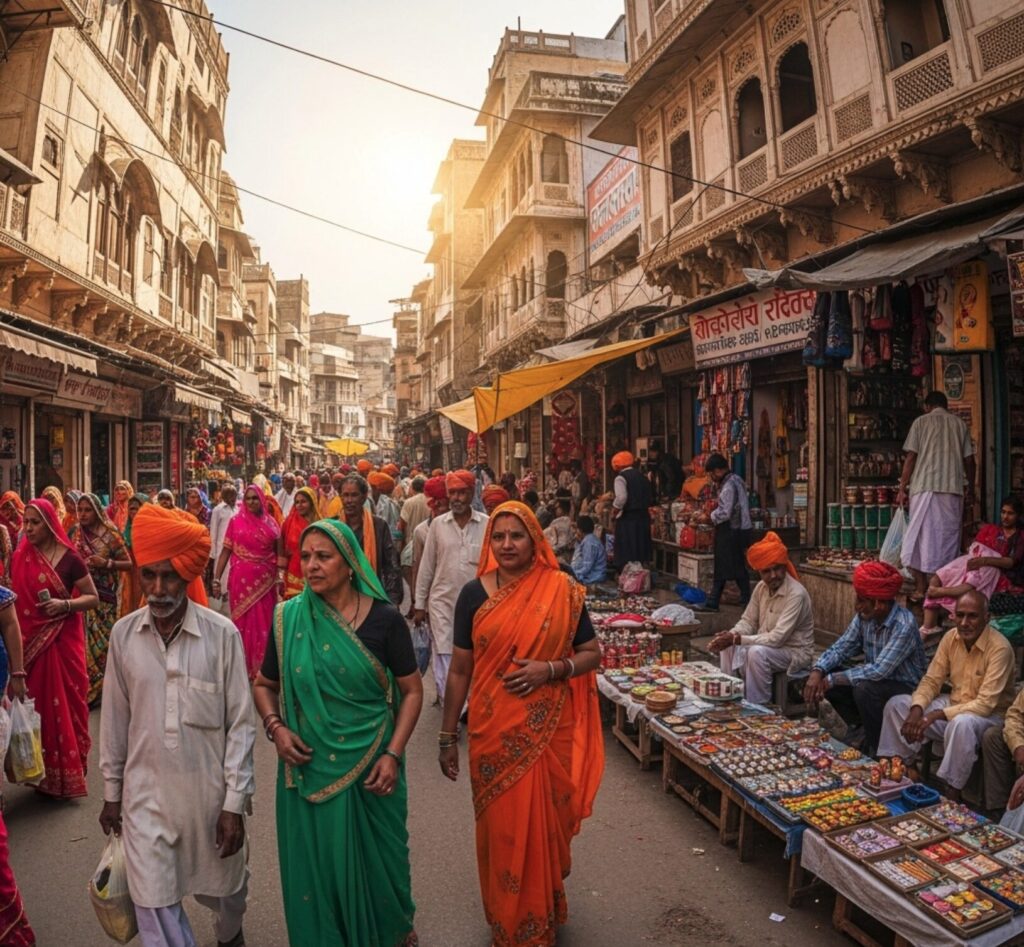
市場の構造と主要株価指数
インドの株式市場は規模・流動性ともに南アジア最大であり、世界的にも存在感を増しています。
主要な取引所は、ボンベイ証券取引所(BSE)とナショナル証券取引所(NSE)の2つです。
BSEは1875年創立のアジア最古の取引所で上場企業数は数千社にのぼり、NSEは1990年代に設立された電子取引主体の取引所で取引高では国内最大となっています。それぞれの代表的な株価指数として、BSEの「SENSEX(センセックス)」(上位30社で構成)と、NSEの「NIFTY50」(ニフティ・フィフティ、上位50社で構成)があります。
これらの指数はインド市場のベンチマークとして広く参照されており、近年も堅調な推移を続けています。
例えば、2024年には総選挙での与党勝利を好感して株価が上昇し、主要指数のNIFTY50やSENSEXは一時過去最高値を更新しました。
インド株式市場は長期的にも著しい成長を遂げており、NIFTY50指数はここ20年で約17倍に拡大したとの試算もあります(2002年から2022年まで、現地通貨ベース)。
特に2016年以降、NIFTY50は9年連続で年間上昇を記録しており、2024年までの5年間平均リターンは年+14.5%に達するなど、力強いパフォーマンスを示しています。企業業績の好調さに裏打ちされた堅調な株価上昇であり、中長期の投資妙味が高い市場と言えるでしょう。
経済成長と株式市場の関係
インド経済は近年世界でも有数の高成長を維持しており、そのダイナミズムが株式市場にも反映されています。
特に「人口ボーナス」による生産年齢人口の増加と内需拡大はインドの大きな強みです。
インドの総人口は2023年時点で約14億人に達し、平均年齢は約28歳と非常に若い構成です。
豊富で若い労働力を背景に、長期的な経済発展が見込まれており、この人口動態上の追い風は旺盛な個人消費や住宅・インフラ需要の増加を通じて株式市場にも大きな恩恵をもたらします。
事実、インドは内需主導型の成長傾向が強く、世界経済が減速局面でも一定の安定性を保ちやすいと指摘されています。
政府も「メイク・イン・インディア」政策に代表される製造業育成策や大規模なインフラ投資を進めており、経済成長を底支えしています。
こうした政策の継続や政治的安定もあって、IMFや世界銀行など主要機関は2025年以降もインドの経済成長率を年6~7%程度と高い水準で予測しています。
高成長を背景に企業の利益も増加を続け、2021年以降インド主要企業の1株当たり利益(EPS)は毎年2桁成長を記録しており、株価上昇に説得力を与えています。このように経済成長と企業業績の拡大が連動する形で、インドの株式市場は長期的にも発展が期待できる状況にあります。
もっとも注意すべきリスク要因も存在します。インド固有の課題として高インフレ率や規制上の不透明さ、新興国ゆえの政治リスクが挙げられます。
また世界経済の動向にも影響されやすく、米国の金融政策次第で海外資金が流出入し株価が変動するといった局面もみられます。
しかし足元ではインフレ率は徐々に安定化し(2024年は食料価格高騰でCPIが一時6%台となったものの、供給改善で沈静化)、政策金利も将来的に利下げに転じる可能性が示唆されるなど、マクロ環境は改善傾向です。
長期的には人口構成や内需という強固な土台があるため、インド株式市場は「高成長余地とボラティリティ(変動)の両面を持つ魅力的な投資先」として位置付けられています。
注目される産業セクター・主要企業
広大なインド経済には多様な産業セクターが存在し、株式市場でもさまざまな分野のリーディング企業が活躍しています。
中でもIT・デジタルサービス分野と金融セクターはインド株式市場を牽引する代表的セクターです。
インドのITサービス企業(例えばインフォシスやタタ・コンサルタンシー・サービシズ(TCS)など)は、欧米企業からのアウトソーシング需要を背景に国際競争力が極めて高く、売上高・利益率ともに世界的に見ても高水準にあります。
このIT分野の成長力はインド市場の象徴であり、今後も海外需要と国内のデジタル化推進の両面から高い成長が期待されています。
金融セクターでは、HDFC銀行やインドステイト銀行(SBI)など大手銀行・保険が高成長する経済を支える形で業績を伸ばしています。特に国内の中間所得層の拡大に伴い、銀行・証券・保険など金融サービスへの需要が増しており、この領域は引き続き注目でしょう。
加えて、政府主導の産業振興策により製造業やインフラ関連も有望なセクターです。電子機器や自動車、電気自動車(EV)、さらには半導体といった製造業分野では、「中国+1」戦略の追い風でインドを生産拠点とする動きが活発化しています。
インド最大財閥リライアンス・グループ(石油エネルギーから通信まで幅広く展開)や、自動車のマルチ・スズキ、二輪車のヒーロー・モトコープ、IT機器製造のフォックスコン(インド拠点)など、製造・インフラ領域でも国内外の企業が積極的投資を進めています。
さらに再生可能エネルギー(太陽光・風力発電やグリーン水素など)も政府の後押しにより成長ポテンシャルが高い新興セクターです。
そして忘れてならないのが国内消費関連セクターで、人口14億人の生活を支える日用品・食品(例:ヒンドゥスタン・ユニリーバ等)、通信(例:Bhartiエアテル)、医薬品(例:サンファーマ)など多岐にわたります。
インド経済の高成長に伴い、これら内需セクターの企業も堅調な成長を続けており、中長期投資では注目の対象です。
代表的企業としては、IT業界のインフォシスやTCS、金融ではHDFC銀行、SBI、エネルギー・通信でリライアンス・インダストリーズ、消費財でインド版P&Gとも言えるヒンドゥスタン・ユニリーバ、製薬で世界的ジェネリック企業のサン・ファーマなどが挙げられます。
インド株式市場はこのように幅広い成長産業セクターへのアクセスを提供しており、「世界有数の高成長市場」として世界中の投資家から注目されています。
参考:大和証券「インド株お2024年の振り返りと2025年の見通し」
日本からインド株に投資する具体的な手段
インドの株式に投資する方法として、日本の個人投資家にはいくつかのルートがあります。
それぞれメリット・留意点がありますので、代表的な手段を整理します。
日本からインド株に投資する具体的な手段
- 国内上場のインド株式ETFを利用: 日本国内の証券取引所(東証)にはインドの株価指数に連動するETFが上場されています。例えば「iシェアーズ インド株 Nifty50 ETF」(証券コード:201A)はNIFTY50指数と連動し、低コストで幅広いインド企業に分散投資できるETFとして2024年に上場しました。また野村アセットの「NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty50連動型上場投信」(コード:1678)なども取引可能です。これらのETFを通じれば、日本の株式を売買するのと同じように円建て・日本時間でインド株市場に投資できます。NISA口座の活用も可能であり、少額から手軽にインドの成長恩恵を取り込める方法です。
- インド関連の投資信託(ファンド)を購入: 証券会社や銀行では、インド株式に投資する公募投資信託が多数販売されています。これらは運用会社がインドの有望企業に分散投資してくれる商品で、「○○インド株ファンド」といった名前で複数存在します。アクティブ運用型で成長銘柄に厳選投資するものや、NIFTY50等の指数に連動するインデックス型ファンドまで種類は様々です。投資信託であれば特定口座を利用でき、税務も国内株式と同様に源泉徴収されるため初心者にも扱いやすいでしょう。購入時・売却時に信託報酬や手数料がかかる点には留意が必要ですが、運用の専門家が企業調査を行う分、自分で個別株を分析する手間が省ける利点があります。
- ADR(米国預託証券)の活用: インドの主要企業の中には米国市場に上場しているADR(American Depositary Receipt)があります。例えばIT最大手インフォシスのADR(ティッカー:INFY)はニューヨーク証券取引所に上場しており、日本の証券会社経由で米国株として購入可能です。ADRは米ドル建てで流動性も比較的高いため、特定のインド企業をピンポイントで投資したい場合に有効な手段です。ただしADRが発行されているのは一部の大企業に限られる点、また円からドルへの為替変動リスクが伴う点には注意しましょう。
- 海外(現地)証券口座を通じて直接購入: インド市場の個別株を直接売買するには、現地の証券会社口座を開設し、外国人投資家登録(FPI)など所定の手続きを経る必要があります。ハードルは高めですが、不可能ではありません。例えばインドの大手証券会社に口座開設し、日本からオンラインで注文を出す方法や、外国株対応のグローバル証券口座(海外専業ブローカー等)を利用する方法があります。ただし現地規制の変更や税制、為替管理など考慮すべき点が多く、一般的な日本人個人投資家にとってはやや複雑です。そのため上記の国内ETFや投資信託、ADRといったルートを使う方が簡便でしょう。どうしても直接個別株を保有したい場合は、事前にインド株式市場の取引制度や現地通貨ルピーの為替リスク、企業の開示情報などを綿密に調べた上で臨むことが大切です。
以上のように、インド株への投資手段は多岐にわたります。
それぞれ流動性やコスト、為替リスクが異なりますので、自分の投資目的や知識レベルに応じて選択するとよいでしょう。
インド市場は長期的な成長期待が高い半面、短期的な変動も大きいので、分散投資や余裕資金での長期保有を心がけるのが基本戦略となります
スリランカの株式市場

市場の構造と主要株価指数
スリランカの株式市場は、首都コロンボにあるコロンボ証券取引所(CSE)を中心に展開しています。
規模としてはインドに比べ小さく、いわゆるフロンティア市場(新興国よりさらに市場規模が小さい未開拓市場)に分類されます。
CSEには約300社弱(296社、19業種に分類)の企業が上場しており、時価総額は2021年時点でおよそ5兆5千億スリランカルピー(約150億~200億米ドル規模)です。
主要な株価指数は、全上場銘柄を含む「CSEオールシェア指数(ASPI)」と、流動性や時価総額の大きい銘柄で構成される「S&Pスリランカ20指数(S&P SL20)」があります。ASPIは市場全体の動向を示す指数で、2021年9月には初めて9,000ポイントを超える史上最高値を記録しました。
その後、スリランカ経済が危機に陥った2022年前後には株式市場も大きく調整しましたが、2023年以降は落ち着きを取り戻しつつあります。2025年6月現在、ASPIは約17,000ポイント台となっており(※高インフレによる名目値の上昇も含みますが)、経済の回復期待を映して再度上昇基調にあります。
スリランカ市場の構造上の特徴として、海外投資家の存在感が挙げられます。
CSEでは外国人も株式売買が可能であり、歴史的に欧米やアジアの機関投資家がスリランカ株をポートフォリオに組み入れる動きも見られました。
ただし近年の経済混乱期には海外資金の流出もあり、流動性は限定的です。また上場企業は地場の有力コングロマリット(複合企業)や銀行、飲料・食品、通信など内需系企業が中心で、輸出型産業の上場比率はそこまで高くありません。
証券市場の規模が小さいぶん、一部の大企業の株価動向が指数全体に与える影響も大きい点は注意が必要です。
経済成長と株式市場の関係
スリランカ経済は過去数十年で大きな変遷を遂げました。
2009年の内戦終結以降、しばらくは年率7~8%台の高成長を達成し、「南アジアの優等生」とも称されました。
これに伴い株式市場も2010年代前半には活況を呈し、一時は世界有数の高リターン市場として注目されたこともあります。
関連:スリランカってどんな国?
しかしその後は構造的な財政・経常赤字の拡大や政治の混乱が影を落とし、経済成長率は次第に減速。
2022年には深刻な経済危機に陥り、対外債務のデフォルト(債務不履行)に追い込まれる事態となりました。
インフレ率が一時50%超に急騰し通貨スリランカルピーも急落、実質GDP成長率は2022年に-7.8%と大幅なマイナス成長を記録しています。
この危機の中で株式市場も暴落し、投資家心理は冷え込みました。
しかし2023年以降、スリランカ経済はIMF(国際通貨基金)の支援プログラムを受けて財政・金融面の再建に取り組んでおり、徐々に回復の兆しを見せています。政府は構造改革を進めつつ、インフレ抑制と金利引下げに成功しつつあります。
実際、中央銀行政策金利は危機時の15%超から2023年末には一桁台(約10%前後)まで低下しました。金利の大幅低下は企業の資金繰りを改善し、債券から株式への資金シフトも促すため、株式市場にとって追い風です。
さらに債務再編(国内外両方)の進展により財政の持続可能性が高まれば、国の信用格付け向上と海外からの信頼回復につながり、株式市場への資金流入増加も期待されます。政府は今後、大型国営企業の民営化(株式市場を通じた売却)を予定しており、市場活性化につながるとの見方もあります。
長期的に見れば、スリランカ経済には地政学的なポテンシャルもあります。
インド洋海上輸送の要衝という地理的位置から物流ハブとしての発展可能性を秘め、教育水準の高さや識字率の高さ(90%超)から人材の質も良好です。
ただ一方で人口動態を見ると出生率低下により将来の高齢化・人口減少が懸念されており、インドやバングラデシュほどの人口ボーナス効果は期待しにくいとの指摘もあります。
スリランカ政府は経済危機を教訓に財政改革や産業多角化を図っており、観光やITサービスなど新たな稼ぎ頭の育成に力を入れています。
株式市場の将来性も、こうした経済構造改革が軌道に乗るかにかかっているでしょう。
直近ではIMF主導の改革で経済は持ち直しつつあり、「経済活動の活発化と低金利により株式リターン拡大が期待される」との現地専門家の声もあります。
実際、今ファンダメンタルズ(業績)の強い銘柄に仕込めば将来的により高いリターンが得られるとの見方も出ており、日本の超低金利と比べてもスリランカ株は魅力的になり得るとの指摘です。
スリランカの成長の熱を感じたいという方は実際に一度いってみるのがよいでしょう。スリランカではまだ公共交通機関が発達していないのでタクシーチャーターで巡るのが一般的です。
以下のサービスで筆者も巡りましたので参考にしていただければと思います。
注目される産業セクター・主要企業
スリランカの産業は、輸出主導型の衣料品産業や農産品(紅茶など)と、国内向けの金融・通信・インフラが二本柱です。
なかでも衣料品(繊維)製造業はスリランカ最大級の輸出産業であり、欧米向けのアパレル生産拠点として発展してきました。
衣料品輸出は同国の輸出収入全体の2番目に大きい柱で、従事者は約30万人にのぼります。
2025年時点では米国との貿易摩擦で高関税の影響を受け苦境に立たされていますが、それでも引き続き重要な産業であり、関連企業としては大手繊維メーカーのMASホールディングス(未上場)や上場企業ではヘイリーズ(繊維・ゴム製品大手)などが知られます。
もう一つの伝統的輸出品がセイロン紅茶に代表される茶葉産業です。紅茶はスリランカを代表する農産品で、上場企業にも茶園会社や農園系企業が複数存在します(例:Dilmahブランドを有する企業など)。紅茶・ゴム・ココナッツといったプランテーション(農園)事業は植民地時代からの歴史ある産業で、国内雇用にも寄与しています。
一方、内需系では金融(銀行・保険)とコングロマリット(複合企業)が株式市場を主導しています。
代表的な上場企業としては、スリランカ最大の企業グループでリゾートホテルやスーパーなど幅広い事業を展開するジョン・キールズ・ホールディングス(JKH)、民間最大手銀行のコマーシャルバンク、同じく大手のサンプス銀行、通信事業のダイアログ・アジアタ(マレーシア資本の携帯通信オペレーター)などが挙げられます。
これら企業はスリランカ国内市場で高いシェアを持ち、経済成長とともに収益拡大が期待される銘柄です。特に銀行セクターは金利低下局面で貸出が増えやすく、今後業績改善が見込まれます。
また、観光・ホテル産業も注目セクターです。スリランカは豊かな自然と文化遺産を有し、観光地として人気があります。内戦終結後は外国人観光客が急増し、ホテルチェーンや旅行業が潤いましたが、コロナ禍と経済危機で一時低迷しました。
今後政治・経済が安定すれば観光業は再び成長軌道に乗る可能性が高く、ホテル経営を手掛けるJKHやAitken Spence、航空業のスリランカ航空(未上場だが今後民営化の可能性あり)などが恩恵を受けるでしょう。
さらに、近年IT・サービス産業がスリランカの新たな成長エンジンとして注目されています。
政府はデジタル経済振興戦略を策定し、スタートアップ支援やIT人材育成に力を入れています。スリランカのIT人材は英語堪能で人件費もインドより割安と評価されており、高スキルIT人材の供給源としてアジア1位、世界でも4位とする調査結果もあります。
海外投資家もスリランカのIT企業やスタートアップに注目し始めており、実際にシンガポールや日本のベンチャーキャピタルが現地フィンテック企業などに出資する動きも出ています。現状ではIT関連で上場している大企業は多くありませんが、将来的にこの分野から有望企業が台頭すれば株式市場の構成も変わっていく可能性があります。
総じて、スリランカ株式市場は従来型の銀行・消費・インフラ企業と、将来型の観光・IT関連が交錯する形で構成されています。経済再建の進展に伴って、まずは銀行や小売など既存産業の業績回復が期待され、次いで新興分野の成長が中長期的なテーマとなるでしょう。
日本からスリランカ株に投資する具体的な手段
スリランカ株式への投資は、インドに比べると一般的ではありませんが、いくつかの方法があります。
日本にいながらスリランカ市場の成長に参加するには、以下のような手段を検討できます。
スリランカ株に投資する手段
- フロンティア市場ファンドへの投資: 日本国内で購入できる新興国株式ファンドの中には、スリランカを含む「フロンティア諸国」に投資する投資信託があります。例えば「◯◯アジア・フロンティア株式ファンド」といった商品では、バングラデシュ・スリランカ・ベトナム・モンゴルなど複数のフロンティア市場の企業に分散投資しています。実際、ハーベスト社運用のアジア・フロンティア株式ファンドはスリランカやバングラデシュの有力企業にも実質的に投資しており、楽天証券やSBI証券を通じて購入可能です。このようなファンドを活用すれば、一国に集中せず分散投資しながらスリランカ株にもエクスポージャーを得られます。ファンドマネージャーが現地調査を行い銘柄選定してくれる点は心強いでしょう。ただしフロンティア市場は流動性が低く価格変動も大きいため、基準価額のブレが大きくなる可能性がある点には注意が必要です。
- 海外ETFの活用: スリランカ単独を対象としたETFは日本国内には上場していませんが、海外市場には存在する可能性があります(例えばロンドンや米国の一部証券所でスリランカ株指数連動ETFが上場していた事例があります)。しかし海外ETFを購入するにはそれに対応した海外株式取引口座が必要であり、一般的な日本のネット証券では扱っていないことが多いです。よって実務的には、スリランカを対象に含む国際分散型ETF(フロンティア市場全般に投資するETFなど)を米国市場等で探し、海外取引口座で買う方法が考えられます。ただ初心者には難易度が高いため、この方法は上級者向けと言えるでしょう。
- 現地証券会社で口座開設・直接投資: スリランカの証券取引所CSEは海外投資家にも開放されていますので、極端な話、現地の証券会社に口座を開設して直接株式を買うことも可能です。CSEのサイトから外国人向けの口座開設案内を取り寄せ、パスポート情報などを提出して手続きを行う形になります。ただ実際には言語や送金の問題もありハードルは高めです。またスリランカは為替規制が厳しい側面もあるため、資金の出し入れに時間がかかる場合もあります。現地直接投資は情報収集や管理の難易度が高いため、一般的にはあまり現実的な手段ではありません。どうしても個別銘柄を直接保有したい事情がない限り、先述のファンド経由などを使う方が無難でしょう。
現状、日本人投資家がスリランカ株に投資する場合、単独でスリランカだけに賭けるというより、他の国と組み合わせた分散投資の文脈で行うケースが多いと考えられます。
スリランカ市場単体は変動リスクも高いため、例えば「南アジアやアジア新興国全般に投資するファンドの一部としてスリランカにも投資している」くらいのスタンスが初心者には適切でしょう。なお、投資する際は現地通貨スリランカルピーの為替変動にも注意が必要です。
経済危機時には大幅に下落した経緯もあり、円から見たリターンが為替で減殺されるリスクもあります。長期的には経済再建が順調に進めば通貨も安定する可能性がありますが、慎重に見極めましょう。
バングラデシュの株式市場
市場の構造と主要株価指数
バングラデシュの株式市場は、首都ダッカのダッカ証券取引所(DSE)を中心に展開されています(第2の取引所としてチッタゴン証券取引所もあります)。DSEには約589銘柄が上場(2020年時点)しており、時価総額は約440億米ドル規模に達します。
主要な株価指数は3つあり、DSEX(ダッカ総合指数)が中核的な総合株価指数です。他にイスラム法に準拠した銘柄で構成するDSES指数や大型株30銘柄のDS30指数が算出されています。DSEXは2013年に導入された指数で、以降のバングラデシュ市場全体の指標となっています。
近年の推移を見ると、2017年11月にDSEXは史上最高値の約6,337ポイントを記録しましたが、その後はやや調整し、2019年末時点では4,433ポイント程度となっています。2020年前後には世界的なパンデミック等の影響も受け一時低迷しましたが、2021年~2022年にかけては再び上昇基調を強め、一時過去高値を更新したとの報道もありました。2023年現在、DSEXは5,000~6,000ポイント台で推移している模様です(※最新データは状況に応じ確認が必要)。
市場構造として、バングラデシュ株は国内個人投資家の売買比率が非常に高い点が特徴です。口座数も増加傾向にあり、都市部を中心に株式投資が広がっています。ただ、機関投資家や外国人投資家の参加は限定的で、市場の厚み(流動性)は先進国やインドなどに比べると劣ります。
また上場企業の多くは、銀行など金融、繊維・アパレル、製薬、通信、セメントなど国内産業を代表する分野です。多国籍企業の現地法人なども上場していますが全体から見ると少数です。
規制面では証券委員会(BSEC)の監督下にあり、市場の透明性向上やIT化(取引の電子化など)が進められてきました。もっとも、過去には証券市場の急騰・急落局面で政府当局が売買停止など介入策を講じた歴史もあり、市場成熟度という点では発展途上と言えます。
経済成長と株式市場の関係
バングラデシュは過去10~15年にわたり著しい経済成長を遂げてきました。
毎年6~8%前後という高い実質GDP成長率を維持し、貧困削減や社会指標の改善でも成果を上げています。その原動力は縫製品(衣料品)の輸出産業と海外出稼ぎ労働者からの送金、そして堅調な国内消費です。
しかしながら、こうした堅調な経済成長にもかかわらず、バングラデシュの経済成長率と株式市場のリターンは必ずしも歩調を合わせていません。たとえば2016~2018年にGDP成長率が7~8%台と加速した局面でも、株式市場は低迷し年初来マイナスの収益率となるなど精彩を欠いた時期がありました。
この背景には、銀行融資の逼迫や市場の流動性不足、投資家の信頼感低下など資本市場特有の構造問題があったと指摘されています。政府当局も株式市場活性化のために、銀行が中央銀行から低利資金を借りて株式投資に回せる措置を導入するなどテコ入れを行った経緯があります。
しかし長期的に見れば、経済の成長が企業業績を底上げし、それがいずれ株式市場にも反映される可能性は十分にあります。
バングラデシュ経済の将来像として、多くの国際機関や投資家がポジティブな見通しを示しています。英国の経済研究所CEBRの予測によれば、バングラデシュは2030年に経済規模で世界28位、2035年には25位に躍進し、2035年には名目GDPが1兆ドルを超える見込みとされています。
2021年時点では世界41位だった経済規模が、わずか10数年で主要新興国に肩を並べる存在になるという大胆な予測です。実際、成長率は今後も平均6~7%台と高位安定が見込まれ(2021~2025年平均成長率6.8%との予測)、人口増加率こそ1%未満と緩やかながらも、総人口は既に1億7千万を超えてさらに増加中です。若年労働力の豊富さと安価な人件費は「アジア最後の巨大フロンティア市場」として世界から注目を集める理由になっています。
もっとも、バングラデシュには資本市場発展のため解決すべき課題もあります。例えば世界銀行の「ビジネス環境ランキング2020」ではバングラデシュは190ヶ国中168位と低迷し、契約の履行や電力供給などインフラ・法制度面の遅れが指摘されています。
これは民間企業の事業環境にも影響し、投資家保護やコーポレートガバナンスの面でも改善余地があります。ただ、ランキングは2019年の176位からは上昇しており改革の進展もみられます。
経済規模に比して外国直接投資(FDI)がGDP比1%強と極めて低水準であることも課題ですが、裏を返せば今後ビジネス環境が整えば海外資本流入のポテンシャルは大きいとも言えます。政府は投資誘致やインフラ整備に注力しており、株式市場も規制緩和やデジタル化を進めて海外投資家を呼び込もうとしています。
まとめると、バングラデシュの株式市場は実体経済(高成長)と金融市場(停滞気味)のギャップを抱えつつも、将来的にはそのギャップが埋まり大きく飛躍する可能性があります。
足元ではインフレ高進や輸入代金支払い難による経常収支悪化など短期不安要因もありますが、中長期的には巨大人口・安価な労働力・輸出競争力という強みを背景に企業の収益拡大と市場拡大が見込まれます。10年以上の長期スパンでは、バングラデシュ株式市場が「次なる成長マーケット」として台頭するシナリオも現実味を帯びてきているのです。
注目される産業セクター・主要企業
バングラデシュ経済を語る上で欠かせないのが繊維(アパレル)産業です。同国は中国に次ぐ世界第2位の衣料品輸出国であり、H&MやZARAなど欧米のファストファッション企業向けの衣料品を大量生産しています。
衣料品産業は輸出収入全体の80%超を稼ぎ、400万人以上を雇用し、GDPの約10%を生み出す基幹産業です。このため株式市場でも繊維関連企業の存在感は大きく、代表的な上場企業にはナイトスター・ファッションやスクエア・テキスタイル、アペックスフットウェア(履物)などがあります。
ただ実際には業界最大手の多くは非上場のオーナー企業で占められており、市場で投資可能な銘柄は限定的です。それでも縫製産業の好不調は国内銀行の不良債権や電力需要など経済全体に波及するため、投資家は常に留意しておく必要があります。
次に重要なのが金融セクター(銀行・マイクロファイナンス)です。国営と民間あわせて多数の銀行が存在し、企業融資や貿易金融を担っています。上場銀行ではBRAC銀行(マイクロ金融大手BRAC系)、ダッカ銀行、イスラミ銀行(イスラム金融)などが挙げられます。
国内経済の拡大につれて銀行の貸出資産も伸びてきましたが、一部では融資焦げ付きも問題化しつつあり、銀行再編・統合の話もあります。健全な銀行の見極めが重要です。また金融包摂の観点から発達したマイクロファイナンス(零細融資)業界もバングラデシュの特色で、グラミン銀行で有名なムハマド・ユヌス氏の取り組みが知られます。関連する金融サービス企業も今後市場に出てくる可能性があります。
さらに注目なのが通信・テクノロジー分野です。バングラデシュは人口規模が大きく、携帯電話やインターネットの普及が経済発展に直結しています。
最大の携帯通信会社グラミンフォン(ノルウェーのテレノール社が筆頭株主)は上場企業であり、常にトップクラスの時価総額を誇ります。通信インフラやデジタル決済、Eコマースなどの新興産業も成長著しく、Bkash(モバイル決済サービス)など非上場ながらユニコーン企業も登場しています。
これらテック系企業が今後株式公開すれば、大型の投資先として注目されるでしょう。
他の主要セクターとしては、医薬品・ヘルスケアがあります。バングラデシュ製薬業は近年品質向上と輸出拡大が進み、アジアやアフリカ諸国にジェネリック医薬品を輸出しています。
上場企業ではスクエア・ファーマ(製薬最大手)やベキシムコ・ファーマなどが著名で、安価な医薬品需要を背景に成長が期待されます。またセメント・建材業界も人口増による都市開発で需要増大中で、ラファージュホルシム・バングラデシュなど多国籍企業傘下の上場企業が存在します。さらにエネルギー(発電・ガス)分野では国営企業の民営化やIPP(独立系発電事業者)の上場などが進めば投資チャンスが広がります。
総じて、バングラデシュの株式市場では繊維輸出を柱としつつ、金融・通信・医薬といった内需・新興産業が成長エンジンとして台頭している状況です。
主要上場企業としては、先述のグラミンフォン、スクエア製薬の他、コングロマリットのベキシムコ(繊維・石油製品・金融など多角経営)、タバコ大手のブリティッシュアメリカンタバコ・バングラデシュ、乳製品のラクシュミコなども知られます。今後、経済規模拡大に伴いインフラ、電力、ITサービスなど新規分野からの上場も期待され、市場の顔ぶれはより多彩になっていくでしょう。
日本からバングラデシュ株に投資する具体的な手段
バングラデシュ株式への投資手段も、基本的にはスリランカと同様に海外フロンティア市場への分散投資という形が現実的です。日本人が単独でバングラデシュの個別株を直接売買するのは難易度が高いため、以下のような間接的手段が中心になります。
- バングラデシュを含む投資信託を利用: 日本国内で購入できる新興国・フロンティア市場ファンドの中には、バングラデシュ企業に重点投資するものや組入比率の高いものがあります。例えば「〇〇・フロンティア株式ファンド(バングラデシュ重視型)」といった商品が過去に設定された例があります(現在募集終了の場合もあります)。あるいは前述のアジア・フロンティア株式ファンドのようにバングラデシュを主要投資先の一つとするファンドも存在します。そうした投資信託を購入すれば、プロの運用者がバングラデシュの有望企業(グラミンフォンやスクエア・ファーマ等)に投資してくれるため、間接的に市場に参加できます。投資信託ゆえに手数料や信託報酬がかかりますが、自分で現地情報を集める手間を省けるメリットがあります。
- 海外ETF・海外ファンドの活用: 米国市場にはかつてバングラデシュ単独のETF(例えばティッカーコードで「FBZ」など)が上場していたことがありますし、現在もドイツのフランクフルト市場にはXtrackers MSCI Bangladesh ETFが上場しています。これらを購入するには海外取引に対応した証券口座(例えば米国株取引が可能な口座)が必要ですが、一部の先進投資家はInteractive Brokersなどを通じてそれらETFを保有しています。ただ初心者にはハードルが高いため、無理に海外ETFを直接買う必要はありません。代わりに先進国市場に上場する新興国ETF(例えばMSCIフロンティア市場指数連動ETF等)の中でバングラデシュ比率が高いものを選ぶ方法もあります。いずれにせよ、こちらも基本的には海外株式を売買できる環境が前提となる点に注意が必要です。
- 現地証券口座で直接投資: バングラデシュも外国人の証券投資が法的には可能です。実際、日本の機関投資家が現地の大型IPOに参加した例もあります。ただ個人レベルで現地口座を開設するのは、言語や手続き面で非常に困難でしょう。強いて言えば、現地に渡航する機会があり信用できる証券会社を通じて口座を作成し、送金・決済を行うという手段になります。しかし市場の未成熟さ(情報開示の遅れや約定の不確実性など)も考慮すると、直接投資はリスクが高く、熟練した投資家向けです。
以上から、バングラデシュ株へは「日本で買えるファンドを通じてエクスポージャーを取る」のが現実的であり、これが初心者にも取り組みやすいでしょう。
なお、バングラデシュ・タカ(現地通貨)は近年減価傾向で、特にエネルギー価格高騰や輸入増で2022年前後に大きく下落しました。為替リスク管理は重要で、長期投資では為替損益もトータルリターンに影響します。
幸いバングラデシュの外貨準備は比較的健全で、政府債務も対GDP比40%弱と低水準(2020年時点)に留まっています。したがって、経済が安定成長を続ければ通貨価値も安定乃至は上昇に転じる可能性がありますが、投資期間中の経済状況や政策動向には常に目配りが必要です。
まとめ:南アジア3市場の魅力と付き合い方
最後に、インド・スリランカ・バングラデシュ3か国の株式市場の特徴を簡単に整理しましょう。
- インド: 南アジア最大で世界的にも有力な新興市場。人口ボーナスと内需拡大、高い経済成長率に支えられ、中長期の企業収益拡大が期待できる。IT・金融・製造など多様な成長セクターを有し、株価指数も堅調に推移。リスクとしてインフレや政策変動、為替変動などあるが、長期分散投資先として魅力度は高い。【投資手段】日本国内でETFや投信が充実しており、ADR経由や直接投資も選択肢。
- スリランカ: 規模は小さいものの潜在力あるフロンティア市場。内戦終結後に経済成長と市場拡大を経験したが、直近で経済危機に直面。現在はIMF支援で再建途上にあり、低金利環境が株式市場を下支え。主力は銀行・コングロマリット・衣料など内需および輸出伝統産業。将来的には観光復興やIT産業台頭も期待。【投資手段】単独では難しく、アジアフロンティアファンド等で間接的に投資するのが現実的。
- バングラデシュ: **“Next 11”**にも数えられる高成長国で、人口規模・成長率ともに非常に魅力的な市場。繊維輸出と巨大な労働力で経済は年7%前後の成長を遂げているが、市場はまだ発展途上で株価の動きは経済と乖離する場面も。しかし長期的には経済規模拡大とともに市場成熟が期待され、2030年代には世界有数の経済大国の仲間入りとの予測もある。主力産業は衣料品、金融、通信、製薬などで、今後これらの企業群が収益拡大すれば株式市場リターンも高まる可能性。【投資手段】日本からは専用ETFがなく、フロンティア株投信や海外ETF経由の投資が中心。直接投資は非現実的。
南アジアのこれら市場は、それぞれ成長性とリスクのバランスが異なります。インドは比較的安定した高成長市場、スリランカは再建期のターンアラウンド型市場、バングラデシュは将来性大だが現時点では流動性に難ありの市場と言えます。
投資初心者の方は、まずはインド株のインデックスファンドあたりから検討し、慣れてきたらバングラデシュやスリランカを含むファンドでエッセンスを取り入れるのがおすすめです。
いずれの国についても、長期投資では現地経済の成長果実を享受できる可能性がありますが、政治的リスク(選挙や政策変更)、通貨リスク、流動性リスクには十分注意しましょう。
幸い、日本国内でも情報は入手しやすくなっており、証券会社のレポートや国際機関の統計、ニュースサイトなどで各国市場の動向をウォッチできます。
例えばインド株はモディ政権の政策や米金融政策の影響、スリランカ株はIMF改革や選挙動向、バングラデシュ株は輸出産業の状況や政策発表などがカギとなります。それらをチェックしつつ、長期的な視点でじっくり南アジアの成長に寄り添う投資を心掛けてください。
南アジア3市場への投資は、日本国内の株式投資とは一味違うエキゾチックさがありますが、その分リターンの潜在力も大きなものがあります。まさに「ハイリスク・ハイリターン」の側面もありますので、余裕資金で分散投資し、長い目で成長を見守る姿勢が大切です。
現地の経済発展と企業の成長を応援する気持ちで、無理のない範囲から一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。将来的にインドが世界3位の経済大国に、バングラデシュが「アジアの新興虎」に、スリランカが危機を克服した安定成長国にそれぞれなった暁には、きっとあなたの資産形成にも嬉しい果実が実っていることでしょう。